48歳の男性です。大学を卒業して電気メ-カ-に勤務していましたが、親の介護のこともあり、地元の大阪に帰ってきて、地元の大手のビル管理会社に入りました。
いわゆるビルメンという仕事ですね。
業界的には大手の会社で、日本国内でも5本の指に入る会社です。前の会社に37歳まで勤めていて、今の会社に勤めて10年になります。
最初は地元の様々なビルの維持管理作業を毎日担当していましたが、現在では現場を離れて、会社全体の総括の仕事と新規の仕事を獲得する営業の仕事をしています。
年収は600万程度です。
ビルメンの仕事内容ときつい部署について
私の勤務している会社は、業界的には大手の会社で、日本国内でも5本の指に入る会社です。前職では37歳まで勤めていて、今の会社に勤めて10年になります。
当初は地元の様々なビルの運転管理作業を個々に対応していましたが、その後、様々な現場を経験することをずっとやってきました。
主な仕事内容は3つです(4つ目は大手だから)
- ビルの管理業務
- ビルの清掃業務
- ビルの警備業務
- 派遣あっせん業務
ビルメンのメインの仕事はビル運転管理業務になります。
それに付随する形での清掃業務、そしてお客様の建物のセキュリテイを確保するのが仕事である警備業務ということになります。
現在では会社としては、必要なところに必要な資格、能力、経験のある人を派遣するあっせん業も行っています。
それらの仕事を一応すべて経験して、現在で現在では現場を離れて、会社全体の総括の仕事と新規の仕事を獲得する営業の仕事をしています。
ビルメンの仕事は薄利多売

大変なのは社業として、いつもお客様第一といいいながら、薄利多売の会社なのです。
それは私の会社に始まったことではなく、業界全体の抱える悩みです。会社の一人当たりの売り上げが他業種に比べて、7がけか6がけ程度になります。
当然、社員の給料も安くなります。
従って、離職率が極めて高いです。
愛社精神の芽生える土壌は、ある程度の収入があってのことで、安い給料ならば、水は高いところから低いところに流れます。
したがって会社としては、新人として会社に入ってきた若者をどれだけ力させずに続けさせるかと言ことに、かなり力を入れています。
病院ビル管理の部署は特にきつい
きつい部門ということになると、病院関係のビル管理を受けている部署がきついです。
元々、病院との契約費用は、他の一般物件よりも低めですし、数年おきに入札を行って値段を下げられるので、人件費が出るか出ないか程度で回しています。
そこの責任者は、「収益が上がっていない、責任者の資質を問う」と会社経営陣からはつるし上げられるのです。
ビルメンの業績と今後の動向について

ビル管理の仕事は、担当している建物の設備の運転管理が主な仕事です。普通紙年間契約あるいは複数年の契約で、所定の金で契約するとします。
そこから人件費と消耗品、事務費用等を差っ引いたものが、会社の収益になります。
その金額は大体10%から15%になります。非常に、羽振りの良いオ-ナ-の物件を管理する場合は20%程度になることがありますが滅多にありません。
具体的には、1000万円の仕事を受けたとしても、人件費でほとんど出ていくので、会社としての純益は100万円程度であるのがほとんどです。
もう少し具体的な事例で記すと、大手のIT企業の会社、時流に乗っている会社の仕事を受けた場合、1000万円に換算したら、300万円程度の収益があります。
一般企業で1000万円のビル管理の仕事を受けると 150万円から100万円程度の収益が上がることが多いです。
そして学校とか市役所の建物のビル管理業務の場合は、1000万円の仕事で収益が200万円から100万円程度になることが多いです。
ただ定期的に入札ということを行うので、毎回ジリ貧になるようになっています。
そういう意味で一番厳しいのが病院関係のビル管理業務ということになります。
病院は1000万円の仕事をうけて収益が50万円程度で、定期的に入札が必ずあります。
私の会社の経営会議では、病院部門のクロ-ジングを進めています。やれば赤になるからです。
逆に需要が高いのが、時流に乗ったIT関係の会社のビル管理業務になり、その獲得に向けて全社一丸となって対応しています。
リモートワークでビルメンの仕事は楽になったのか?

私の会社はビル管理を売り物にしている会社です。
社員は1000人以上います。
そのうち、内勤の人間が50人ほどいて、他の人間は現場に出向いて、あるいは現場に常駐して様々なビルの科的空間の維持の為に多くの設備の運転管理を実施しています。
内勤の人間はリモートワークの導入で、最終的には通勤の苦しみから解放されて、体が楽になった人間が沢山います。
今のスタイルが軌道に乗るまでは、設備機器の整備、熟練等が必要で大変苦労はしました。
情報交換の必要性が、以前よりも感じるようになったのも事実であります。
現実にはすべてリモートでは解決しない
一方内勤以外の現場の人間にしてみると、リモートワークの導入はありがたい事ではあるが、役務提供型の仕事なので、そのまま,乗っかることが出来ないもどかしさがありました。
現場にはいかないとしこ度が始まらない、お客様の為に役務を提供できないということで、苦労しています。
今もそのジレンマ、世間の風潮に置いていかれているという感じは全社員がいつも感じています。
基本的には、現場には出ないと始まらないが、会社には出る必要ないということが社内に定着し始めました。
いわゆる直行直帰という形が会社に浸透してきたのがコロナの自粛騒ぎが始まった半年ほどたってからのことでした。
それ以降、自宅から担当しているお客様のビルに直接出かけて、求められている業務をこなし、その後は自宅に戻るということが一つのスタンダ-ドにはなっています。
月に一度の全体ミ-ティンク゛は会社から支給のタブレッとで行うようにしています。
今後ビルメンを目指すために重要な2つのこと

ビル管理業務は、役務提供型の仕事なので、現場に体を運んでナンボというところがあります。
従って、コロナの影響で様々な制約を守ることが求められても、応じられないことはあります。
そこを工夫して、安全管理を担保しつつ、上質な仕事を提供するための工夫を業界全体として進めています。
資格体系がビル管理業界ではきっちりしている会社が多いです。
その根拠は、現場経験と電検の資格とか、ビル管の資格とかが中心になります。
電検の資格は取っておくべき
前者の電検の資格は非常に重宝されていて、無資格の30年のビル管理職人よりも、数年のビル管理経験有りの電検保持者の方が上に見られることがあります。
採用情報を見ればすぐにわかることですが、電検資格があるとそれだけで採用の時に有利に働くのは間違いないです。
だから、勉強する時間、機会があれば取得しておくことを強くお勧めします。
転職ありきでキャリアアップを考える必要がある
それと、業界全体の人の流れのことになりますが、ステップアッブというのが一つのスタンダ-ドにはなっています。
最初は無資格、無経験である会社に入り、現場を様々に経験して、それと同時に危険物取扱経験者とか電検3種の資格を順次取っていくのです。
そして、今いる会社から一つか二つ上の会社に転職するということが割合よく起きています。
これは、従来の日本の会社での倫理観からすると、タブ-に該当することになります。ただビル管理業界全体の給与が低いので起こるべくして起きていることになります。
今から、この業界のに入る人は、各会社から取り合いになるような人になることを目指して入ってくるべきでしょう。
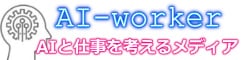

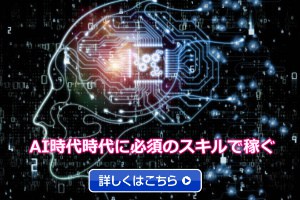
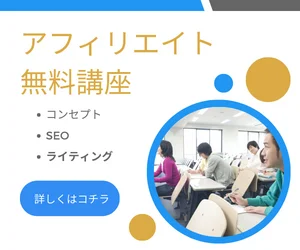
あなたの業界の意見お待ちしています!