貨幣処理機器業界で10年働いていて33歳になります。年収は600万程度です。今回はこの業界の将来性について、現状の問題点と共に真剣に話しておきたいと思います。
【 貨幣処理機業界が抱える問題点 】
- キャッシュレス化による現金流通量の減少
- 銀行の店舗統廃合による店舗減少による販売先の減少
- 電子マネー台頭による現金処理機不要の流れ
- 通販の成長による店舗取引減少
- 貨幣流通にかかるコストの問題化
電子マネーで貨幣処理機の仕事は少しずつ減っている

貨幣処理器業界の現状は、銀行の店舗統廃合によって出納機類のニーズの低下や電子マネーの広がりによる現金流通量減少という逆風があります。
一方キャッシャーや現金管理者の負担軽減のための現金処理機の導入増加やセルフやセミセルフレジ浸透による店舗当たりの自動釣銭機台数の増加などの追い風となる要素もあります。
しかし、将来性に関してはかなり低いと想定します。
キャッシュレスや電子マネーという言葉が、新聞やニュースで耳にしない日は無く、政府としても2027年までにキャッシュレス決済比率を40%までに引き上げるという目標があります。
電子マネーは現状ではさまざまな業者が各社オリジナルのものを出して、赤字を出しながら利用者数を増やしています。
また、電子マネーを使える場所やサービスも増えてきています。
最終的に現物の貨幣が一切無くなるということは考えにくいですが、貨幣流通量は下がり続けていくと考えています。
貨幣流通量が下がる理由は他にもあります。
流通という以上、貨幣を作る人も必要であれば運ぶ人も必要で、そのコストだけでも日本全体で数兆円規模ともと言われています。
人手不足といわれている現状では、貨幣の流通に人手をかけるのはもったいないと思われても仕方ないと思います。
電子マネーの便利さと貨幣の流通コスト考えると、貨幣の流通量が減るのは当然のことであり、それに伴い貨幣処理機のニーズも減っていきこのままでは業界は衰退すると思います。
貨幣処理業界のAIロボットの導入事例
製品の物理的な耐久を評価する場合にAIロボットを活用しています。
ロボットは人と違い基本的にはインターバルなしで動かし続けることができるので、日中夜問わず動かし続けることで耐久確認期間を短縮させることができます。
また、設定した動作を正確に実行し続けることができるので、人がやると毎回バラバラな動きになってしまい正確性の欠ける評価になってしまうところをロボットがやることで正確な評価になります。
例えば、同じ箇所に一定の力をかけて離すという耐久を何万回もやろうとしても、人間がやると力も位置も毎回バラバラですがロボットだと力も位置も正確な状態で最後までやり続けることができます。
製品を作る現場でもロボットが導入されていて、ねじ締めや部品の組み付けなどをロボットがやっています。
検査もロボットがやっていて、ロボットが組み立てたものをロボットが検査しているという状態です。
ロボットに部品を供給したり、ロボットが停止した場合に原因を探り修正したりという作業を人間が行っています。
ロボットによって節約できた工数分を人の削減に充てることはせずに、1人1人にかかる工数を減らしてロボットでできない作業をする時間にあてたり、残業をする時間を減らしたりするという方向性です。
貨幣業界の仕事がAIに奪われないようにすべきこと

製品の組み立て作業などはロボットが行っていて、そのロボットに動作を教えている(入力している)のは人間です。
最適な動きやツールの配置などはまだまだ人間が考える必要がありますが、そのうちAIに取って代わられると考えています。
ただし、ロボットの形やツール自体をAIが考えるのは難しいと思います。
複雑な作業をするためにどのようなロボットの形やツールを作成する必要があるかを考えるという仕事は残るはずなので、そういった分野のノウハウを今のうちに溜め込んでおく必要があると思います。
そのためにはエンジニア系の仕事は重要ですね。
そうしておけばいざ仕事がすべて奪われそうになったときでも、どんなロボットが必要か、どんなツールを持たせる必要があるかを考える人は必ず必要になるので、貯めておいたノウハウが役に立つと思います。
個人的にAIに仕事を奪われないためにやっていることは、常に新しいアイデアや特許などを考えることです。
新しいメカの機構や構造をAIが考え出すのはまだまだ難しいと思いますので、そういう部分でAIに引けをとらないように常に新しいものを考えるようにしています。
また、特許などもAIが独自で生み出せるものではないとおもっていますので、いざAIのレベルがある程度複雑なものを考えられるようになってきたとしても、それよりさらに複雑なものを考えられるように常に頭を鍛えています。
不具合解析なども人間が現物を目で見ていろいろな要素から判断する必要があります。
そういった分野の仕事も最後までは残るはずなので、現物を目で見て確実に現象をとらえらえるくせをつけたり、色々な方向から不具合の原因の目星をつけられるように日ごろから積極的に不具合解析などに取り組んでいます。
貨幣処理業界で将来役立つ資格や勉強法

貨幣処理機業界でメカを設計しようとしている方がいたら、エレキ分野やソフト分野などのメカ以外のスキルを持つことをおすすめします。
私はメカの設計者をしていますので、貨幣処理機ならではの機構や構造は詳しいですが、その知識が他の装置や一般的な機械に役に立つかは疑問です。
貨幣処理機を作らなくてよくなってしまったら、私の場合はできることが無くなるかゼロから学びなおす必要があります。
その点、エレキ的な知識やソフト的な知識は応用が利くと考えています。
世の中が電子マネーだけになったとすると貨幣処理機は不要になりますが、電子マネーを読み取るリーダーは必ず必要になるはずで、町のいたるところに置かれることになると思います。
リーダーを構成する要素におけるメカ部分の割合はほぼ筐体部分しかなく、メカ設計者の介入する部分は極めて少ないです。
それに対して、エレキ部品は表示部やリーダー読み取りのアンテナ、通信機器モジュールなど多くの要素がありエレキ設計者の介する部分も多いです。
また、ソフトに関しては通信に関する部分や電子マネーのアプリなど複雑な部分が多くあるので、ソフト設計者はメインで活躍できると思います。
設計以外の分野の方でも、現金処理機は無くなるもしくは減っていくものと考えて、幅広い分野で活躍できるようにスキルをみがいたほうがいいと思います。
貨幣処理機という「モノ」自体は貨幣の流通量が減ると当然不要になっていきます。
貨幣に関するサービスや便利なシステムなどの「コト」に関する部分では業界内でも需要があるとおもいます。
物を作れば売れる時代ではなくなってきたので、サービスやシステムを考える力のある方ならばこの業界でもまだまだできることはあると思います。
ただ、漫然とすごすのではなく将来を見越した勉強をしていかないとAIの進化スピードが速いので怖いですね・・・。
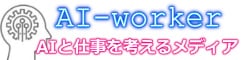

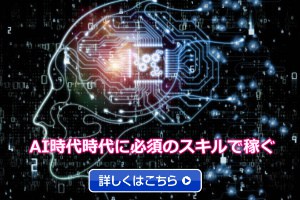
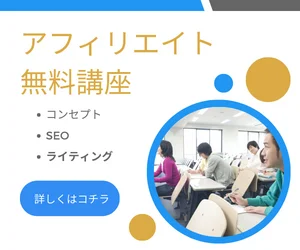
あなたの業界の意見お待ちしています!